こんにちは、PM事業部の吉田純です。
住宅セーフティネット法(正式名称:「住宅確保要配慮者に対する住宅の供給の促進に関する法律」)は、高齢者、低所得者などの住宅確保要配慮者(以下、要配慮者)が、住まいを見つけやすくするための法律です。
令和7年10月1日に施行された改正法のポイントをわかりやすくご紹介します。
セーフティネット制度見直しの背景
2030年には、単身高齢者世帯が900万世帯に達する見通しです。
また、持家率の低下などの影響により、今後は要配慮者の賃貸住宅へのニーズが一層高まることが予想されます。
一方で、孤独死や家賃滞納、死亡後の残地物処理など、オーナーさまにとってリスクや負担になるような課題が指摘されてきました。
令和7年の法改正では、オーナーさまが安心して要配慮者にお部屋を貸し出せるよう、支援体制の強化が図られています。
【改正①】 オーナーさまと要配慮者の双方が安心して利用できる市場環境の整備
◆「賃貸契約が相続されない」仕組みの推進
終身建物賃貸借の認可手続きを、「住宅」ごとの認可から「事業者」としての認可へと簡素化。
認可を受けた事業者は、対象物件を届け出るだけで終身建物賃貸借契約の締結が可能になります。
終身建物賃貸借とは、賃借権が相続されない
契約であり、入居者が亡くなった時点で確定的に契約が終了するので、次の契約までの手続きをスムーズに進めることができます。
◆「残置物処理に困らない」仕組みの普及
オーナーさまと居住支援法人※との間で「委任契約」を結ぶことができるようになり、居住支援法人が受任者として、入居者死亡後の残置物の整理・撤去などを行えるようになります。
※ 住宅セーフティネット法に基づき、居住支援を行う法人として、都道府県が指定するもの。
◆「家賃滞納に困らない」仕組みの創設
要配慮者が利用しやすい家賃債務保証業者を国土交通大臣が認定する制度を創設。
住宅金融支援機構の家賃債務保証保険によって、要配慮者への保証リスクが低減します。
【改正②】 居住支援法人等が入居中サポートを行う賃貸住宅の供給促進
「居住サポート住宅」を創設。
居住支援法人等と貸主が連携し、日常の安否確認や見守りを行い、生活や心身の状況が不安定化したときは、自立相談支援機関、福祉事務所、高齢者福祉の相談窓口などの福祉サービスにつなぎます。
【改正③】 住宅施策と福祉施策が連携した地位の居住支援体制の強化
◆国土交通大臣および厚生労働大臣が共同で基本方針を策定。
◆市区町村による居住支援協議会※設置を促進(努力義務化)し、住まいに関する相談窓口から入居前・入居中・退去時の支援まで、住宅と福祉の関係者が連携した地域における総合的・包括的な居住支援体制の整備を推進。
(※地方公共団体の住宅部局・福祉部局、居住支援法人、不動産関係団体、福祉関係団体等を構成員とした会議体。)
賃貸オーナーさまが受けられる支援
改修費に係る補助
住宅確保要配慮者専用賃貸住宅または居住サポート住宅は、基準を満たさなければ登録できません。
そのために、バリアフリー改修や、耐震改修などの改修工事を行った場合、かかった費用の3分の1の補助金(上限50万円/戸)が支給されます。
(※支援を受けるには、着工前の事前申請が必要です。補助の対象は認められた工事内容に限られ、改修後の性能にも基準があります。
また、補助内容は自治体によって異なる場合がありますので、詳細はお住まいの自治体へご確認ください。)
家賃低廉化に係る補助
要配慮者が無理なく暮らせるよう、家賃を周辺相場より低く設定した場合、その補助として月額最大2万円/戸までの補助金が支給されます。
(※補助を受けるには、事前に登録住宅としての申請・認定が必要です。対象となる入居者は、自治体が定める基準を満たす方に限られます。
また、申請手続きや実績報告が毎年度必要な場合もありますので、詳細はお住まいの自治体にご確認ください。)
いわき土地建物では、7年連続県内売上No.1・2024年不動産仲介件数3,932件の実績を活かし、アパート・マンションなど賃貸物件オーナー様へきめ細やかなサポートを行っています。
「修繕コストの増加が不安」「空室が増えて収入が安定しない」「管理が負担になってきた」など、オーナー様のお悩みに経験豊富なスタッフが解決策をご提案いたします。
現在、他社で管理中の物件についてもご相談可能です。
まずはお気軽にお問い合わせください。
【電話】0246-26-0303
【お問い合わせフォーム】https://www.iwaki-tt.co.jp/forrent/hope-form/


 お問い合せ
お問い合せ
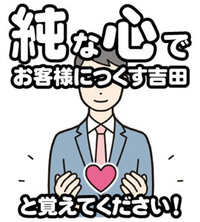
 0246-26-0303
0246-26-0303